(以下の文章は、僕が、2004年の年末から2005年の1月にかけて、大学1回生のときに書いた、Frantz Fanon(フランツ・ファノン)の思想の変遷についてのレポートの内容です。)
「ファノンの思想が『ネグリチュード』から『全的人間』へと移行したこととベルベル問題との因果関係」
<テーマ設定の理由>
『革命の社会学』の序文の「植民地主義の死とは、被植民者の死であると同時に植民者の死である」(Fanon,1984,p.14)という言葉に、私は非常に感銘を受けた。この文章は、ファノンがさまざまな違いを乗り越えて、「人間」という視点に立っていることを示しているからである。独立戦争という異常事態のなかでは、ただ敵を打ち倒し独立を勝ち取ればいいと考えられがちであるが、ファノンはそうではなかった。ファノンは、敵であるコロンたちも植民地主義の犠牲者であるとし、解放闘争を通じて彼らも「人間」を取り戻さなければならないと考えていたのである。私は、どうしてファノンがこの達観ともいえる境地にいたることができたのかということに非常に興味を抱いた。
しかし、そんなファノンもはじめから「人間」という視点に立っていたわけではないことが、「文化とポストコロニアル批評ⅡL」の授業を受ける中で、また、海老坂武の『フランツ・ファノン』を読む中で、徐々に分かってきた。
ファノンの思想は彼の生涯を通じて、黒人第一主義の「ネグリチュード」から人間第一主義の「全的人間」へと徐々に変化したものなのである。その変化の最大の要因は、サルトルの「黒いオルフェ」が彼に与えた影響の大きさであろう。しかし、それだけで全面的にファノンの思想が「全的人間」へと移行したわけではない。
それならば、いったいなぜファノンの思想は「ネグリチュード」から「全的人間」へと移行したのであろうか。その答えは、ファノンが、フランスとアルジェリアの戦いという大問題がある一方で、アルジェリア人の内部にも、同じアルジェリア人であるにも関わらず、アラブ人による黒人の抑圧や弾圧という問題があることに気づいたためではないかと、私は考えた。
この考えにいたった理由は、アルジェリアはアフリカの国であるにも関わらず、授業中に視聴した映画『アルジェの戦い』のなかでも、ファノンの著作の中でも、アルジェリア人として現れているのはアラブ系の人々のみで、アルジェリア人の黒人というものが一切登場しなかったためである。黒人はマイノリティーであり、同じアルジェリア人であっても、多数派であるアラブ系住民によって差別を受けていたのではないかと考えたのである。
しかし、もちろんアルジェリアを含む北西アフリカ一帯のマグレブという場所は、8世紀にアラブ人が侵入し始めて以来、アラブ人とイスラム教によって特徴付けられる土地であり、黒人が少なくアラブ人が多数を占めていたとしても何ら不思議はない。
それにも関わらず、アルジェリアで黒人が弾圧されていたのではないかと考えた理由は、アルジェリアと同じ北西アフリカに属するモーリタニアでは、数百年前から現在までも長らく黒人の奴隷所有が続いているからである。モーリタニアでは、何度も奴隷制廃止が行われているが、実際には未だに、白ムーアと呼ばれるアラブ系住民がハラティーンという奴隷を何世代にもわたって所有しつづけているのである。これまでの奴隷制廃止によって解放奴隷となったアフリカ系モーリタニア人もいるが、彼らも依然として抑圧の対象となっている(Bales,2002,p.116-133)。一部国境線を接し、地理的に近いアルジェリアとモーリタニアならば、社会構造も似通っており、アルジェリアでも黒人は抑圧の対象となっているのではないかと考えたのである。
しかし、実際にはアルジェリアには黒人はほぼいないに等しいことがわかった。アメリカのCIAによると、アルジェリア人の人種構成はアラブ系ベルベル人が99%である。ただし、自らをベルベル人であるとして、アラブ系住民との境界線をはっきりと引いている人々は都市のアラブから離れ、そのほとんどが山岳部に居住している(CIA,2005.1.13更新)。日本の外務省によると、アルジェリア人の人種構成はアラブ人80%、ベルベル人19%なので、この19%がベルベル人と自称している人々であろう(外務省,2005.1.21取得)。
しかし、黒人がいないからといってこの国に差別が無いわけではなかった。アルジェリアでは、黒人ではなくベルベル人がアラブ人から差別を受けているのである。そのことを受けて、先ほどの、「なぜファノンは『ネグリチュード』から『全的人間』へと移行したのか」という疑問の答えを修正し、「ファノンが、フランスとの戦いの裏側で、アルジェリアの内部にアラブ人によるベルベル人の差別の問題があることに気づいたためである」という仮説を立てた。
<レポートの目的と構成>
このレポートの目的は、ファノンが「ネグリチュード」から「全的人間」へと移行した理由が、アルジェリアに内在するベルベル人への抑圧を発見したことであるということを検証していくことである。
そして、ファノンの、「ネグリチュード」から「全的人間」への思想の変化を時系列にそって検証していく。まず、ファノンの中の「ネグリチュード」と「全的人間」の2つ立場について、次に、「黒いオルフェ」の影響について、以下順に、フランス留学時代の「ネグリチュード」について、アルジェリアへの転勤と解放闘争開始時のファノンについて、ベルベル人について、マグレブのアラビア語化について、ベルベル主義者騒動について、メルーザの虐殺について、国境のベルベル人難民について、外国人としてのファノンについて、『革命の社会学』にみる「全的人間」の兆候について、「全的人間」への移行について、独立後のアルジェリアのベルベル問題について、それぞれ述べていく。
1. 2つの立場
上でも述べたように、アルジェリア戦争を通じて「人間」の回復を求め続けたファノンも、はじめから「人間」という視点に立っていたわけではない。ファノンの思想は常に揺れ動き、
「一方の極に頭をぶつけては引き返し、他方の極にむかうとこれにつまずいてまた引き返すというように二つの立場の間で堂々めぐりを繰り返していた」(海老坂,1981,p.24)
のである。
その2つの極とは、「ネグリチュード」と「全的人間」であった(海老坂,1981)。「ネグリチュード」とは、植民地支配に抵抗するために創り出された、黒人に属するものを優れたものとし、白人に属するすべてのものを否定するという考え方である。それに対して、「全的人間」とは、「皮膚の色をしかと直視した上で、なおかつ白-黒を超えて絶対的に肯定しうる人間」(海老坂,1981,p.25)、ひいてはさまざまな違いを乗り越えて、他人を自分との違いによってではなく、その人自身として受けとめることのできる人間のことである。
2. 「ネグリチュード」と「黒いオルフェ」
ファノンの目指すものが、「ネグリチュード」から「全的人間」へと変化した理由は、サルトルの「黒いオルフェ」が彼に与えた影響によるところが大きい。サルトルはネグリチュードを批判し、「白人の優越性に対するアンチテーゼ、弁証法の否定的契機として相対的に位置付けた。」(海老坂,1981,p.121)そのことによって、サルトルはファノンが「『黒い皮膚』に閉じこもることを不可能にさせた」(海老坂,1981,p.122)のである。
しかし、
「ファノンは、『黒いオルフェ』の読書をとおして、一気に皮膚の色の誇りをかなぐりすてたわけではなかった。最終的にはネグリチュードを乗り越える必要があることに同意しながらも、黒人意識は『絶対的密度』としてそれ自体で充足していると主張」(海老坂,1981,p.123)
していた。
つまり、ファノンは理論としての「黒いオルフェ」の正しさを認めてはいたが、「ネグリチュード」から他のものへと全面的に移行する意志はこのときまだ持ち合わせていなかったのである。
「『黒いオルフェ』は一つのきっかけ、それも決定的なきっかけを提供したが、彼に出口を差し出したわけではな」(海老坂,1981,p.124)
かったのである。
サルトルの「黒いオルフェ」は、後に「全的人間」と呼ばれるものへの方向を示しただけで、そこに至る道順までは教えてくれなかったのである。したがって、ファノンもこの時点では、後に「全的人間」呼ばれるものの可能性に疑問を抱いていたのであろう。
3. 「ネグリチュード」への執着
では、「全的人間」という概念がファノンの中でできあがったのはいつであろうか。はっきりと「全的人間」の概念をみてとれるのは、1961年に発表されたファノン最後の書である『地に呪われたる者』の文章の中である。少なくとも、この文章が書かれたときにはファノンの中に「全的人間」の概念はあったことになる。しかし、思想というものは突然、前触れもなくできあがるものではない。もっと以前からその萌芽はファノンの中にあったはずである。
1948年に発表されたサルトルの「黒いオルフェ」を参照し、心揺り動かされてもなお、ファノンが「ネグリチュード」への思いを捨てきれなかったことは先ほど述べた。したがって、「全的人間」の概念が現れるのはこれ以降である。つまり、「全的人間」という概念は、1948年から1961年の間のどこかで生まれたということになる。
1952年に発表されたファノンの第一作、『黒い皮膚・白い仮面』の中にもまだそれを見て取ることはできない。なぜならば、この本を書いていた当時のファノンは、フランスでの白人からの差別に対する自己肯定の武器としてなんとしても「ネグリチュード」が必要だったからである。
1946年からフランスのリヨンで学生生活を送っていたファノンは、フランスへの留学中に、「黒人の生体験」に描かれているような、黒人である自分への差別を体験し、一時は神経衰弱に陥るという状態であった(海老坂,1981,p.115)。故郷マルチニック島での幼少時代には、混血で、なおかつ島のエリートであったことから、心のどこかで自分を黒人ではなく白人だと思っていたファノンはこの体験によって大きな衝撃を受けたに違いない。
フランスで受けた、黒人である自分への全否定はファノンの心を深く傷つけた。その傷によって折れかかった心の支えとしてファノンが見出したのが、エメ・セゼールが説いた、黒人性の肯定であり、それによって白人性を否定的に捉える「ネグリチュード」であった。自分を攻撃してくる白人に対抗し、ある意味では生き残るために、ファノンには「ネグリチュード」が必要だったのである。
4. アルジェリア解放闘争の始まり
その後、「ネグリチュード」を引きずったまま、1953年にファノンはアルジェリアのブリダにある精神病院へ転勤する。やはり、ファノンを「全的人間」へと導いたのはアルジェリア、またはアフリカでの体験であったということになる。そして、ファノンがアルジェリアに到着してからほぼ1年後の1954年、アルジェリア解放闘争が始まる。さらに1年後の1956年に、アルジェリアの現状に対する嘆きとフランス当局への怒り、そして医師としての自分の無力さから、ファノンはアルジェリア駐在相ラコストに辞任状を提出する。
「フランス警察、フランス軍隊の弾圧を、医師として彼はまのあたりに見る立場にあった。大量殺戮の場に居合わせたがために、肉親を殺されたがために、拷問を蒙ったがために、精神障害の新たな犠牲者たちが次々にブリダの病院に送りこまれてきた。」(海老坂,1981,p.186)
こういった状況のもと精神障害の患者たちに治療を行うなかで、ファノンはアラブ人たちにリヨン時代の自分を重ねていたに違いない。この時点での彼のアルジェリア人に対する認識は、「アルジェリア人=アラブ人」であり、「アラブ人=フランス当局による弾圧の被害者」というものであっただろう。ブリダの精神病院ではアラブ人との接触しか持てなかったファノンがこのような考えを持ったことは当然のことである。しかし、現実には解放闘争が始まる以前から、アルジェリアには、フランスによる抑圧と弾圧の裏側で、アラブ系住民がベルベル人を抑圧し、弾圧するという状況があったのである。
5. ベルベル人
ベルベル人とは、「北西アフリカに住み、ベルベル語を話す民族」(日本大百科全書,2005.1.21.取得)のことであり、現在のアルジェリアにおいては人口の19%を占めている人々である。
「ベルベル語使用地域の大部分は、中世以降、様々な中央権力と衝突を繰り返してきた地域であり、中央権力はこれらの地域を持続的管理のもとに置くことはできなかった。ほとんどの場合、これらの地域はそれぞれ自律的な政治生活の場を構成する。中央権力の影響やその行政管理が直接に及ぶことは稀だったため、アラビア語が主流である都市の伝統が伝わることも難しかったのである。」(Chaker,2000,p.188-189)
このように、ベルベル人は都市のアラブ人とは一線を画した生活を送っていた。そのため、「アルジェから約五十キロ、もっとも近い街」(海老坂,1981,p.143)であったブリダの病院でファノンがベルベル人と接触したという可能性はきわめて低いと考えられる。ブリダの精神病院は、たとえ患者がいたとしても、アトラス山脈の高地地方に住んでいたベルベル人たちとは何の関係もなく、もっぱらアルジェ周辺の都市部の西欧人とアラブ人患者のためだけに運営されていたのであろう。したがって、ファノンはベルベル人について、またアラブ系住民がベルベル人を弾圧していることは、アルジェリアで働き始めた当初は知らなかったと考えられる。
6. マグレブのアラビア語化
ベルベル語はイスラム教の侵入以来、常にアラビア語化の波にさらされていた。独立を果たした近年では、ベルベル語は国家による明白で敵対的なアラブ化・アラビア語化という言語政策に直面している。
マグレブ諸国では、
「言語的多様性は国家統一(l’unité nationale)に対する危険、分離への一歩として受けとめられた。言語の統一は国家建設(la construction de la Nation)を完遂する要素でなければならな」(Chaker,2000,p.189)
いという考えのもと、
「言語政策の根本的目標の一つはベルベル語の根絶である」(Chaker,2000,p.189)とされたのである。その現れとして、「マグレブ諸国の憲法はすべて、国家をアラブ・イスラム教国として定義」(Chaker,2000,p.189)している。
アルジェリア政府が推し進めるアラビア語化の目標は、
「すべての分野からのベルベル語の完全な排除である。例えば1989年まで、ベルベル語は各種の協会・団体活動においてまで禁じられていた。このような強固な禁止があったために、1962年から1989年まで、アルジェリアのどの公文章にも『ベルベル』という言葉は見当たらなかったほど」(Chaker,2000,p.191)
であった。
また、アラブ人であっても「公式の地位を持たない方言アラビア語(民衆の言語であり、ベルベル語に強く影響を受けている)」(鶴巻泉子,2000,p.198)を使用している人々が存在する。おそらく、彼らの話すアラビア語も、ベルベル語と同様に弾圧の対象となったであろう。こうしたベルベル語排除の動きは独立後に目だって活発化し始めた。
しかし、ベルベル語・ベルベル人に対する迫害は独立後に突然巻き起こったわけではなく、独立以前からアルジェリアにおいて大きな問題とされていたのである。
「『アラブ対ベルベル』という対立の形で表現される政治性は、植民地時代から現代に至るまで、アルジェリアの政治(特に独立後のネイション・ビルディングの過程)にとりわけ深く根ざした問題」(鶴巻泉子,2000,p.198)
なのである。
さらに、
「マグリブのナショナリズムは1925年頃に遡るが、ナショナル・アイデンティティや目標とされた国家は、最初から常にアラブ・イスラム教に基づいて定義され」(Chaker,2000,p.190)
ていたのである。
7. 「ベルベル主義者騒動」
このようなベルベル人排除の動きに対抗するためにベルベル人たちが1948-49年に起こしたのが、アルジェリア・ナショナリスト党(PPA-MTLD)内での「ベルベル主義者騒動」である。
このとき、
「ベルベル主義活動家は、党執行部の主張(「アルジェリアはアラブ・イスラム教国である」)に対し、アルジェリア人民のアルジェリアという主張(「アルジェリアはアラブでありベルベルである」)を対置しようとする。[その結果、]数ヶ月に及ぶ激しい抗争の末、ベルベル路線主義者たちは党から除名され、激しく追及された」(Chaker,2000,p.194)
のである。
この事件は、一方が強硬な姿勢で弾圧を始め、それに対抗するためにもう一方も同様な態度にでて、最後には話し合う余地までも失われてしまうという点で、サルトルが言わんとした、白人の「白い普遍性」に対抗しようとした黒人の「ネグリチュード」が袋小路に陥った状態と同じである。
ただし、この事件はファノンがアルジェリアに転勤してくる以前の出来事であった。したがって、アルジェリアで働き始めた当初は、ファノンもこのことについては知らなかったのではないかと思われる。では、ブリダの病院ではベルベル人に対する迫害について知り得なかったファノンは、いつどこでベルベル人について知ることとなったのだろうか。
8. メルーザの虐殺
1957年1月にファノンはチュニスのFLN指導部に合流するためチュニジアへと渡り、FLNのスポークスマンとしての情宣活動、医師としての病院内外での医療活動、チュニス大学での講義、FLN機関紙の編集と執筆などの活動をはじめていた(海老坂,1981,p.187)。
その年の6月、メルーザ村での虐殺事件が起こる。メルーザの虐殺とは、「コンスタンチーヌのメルーザ村の村民数百名が一夜のうちに全員殺された事件」(海老坂,1981,p.191)のことである。この事件はFLNの構成員が起こしたことであり、「本来は裏切者だけを処刑するはずであったのが、現場の指揮官が見せしめのため老若男女を問わず全員殺してしまった」(海老坂,1981,p.191)というのが真相であった。
虐殺や拷問の結果として、人間がどのような悲劇的状況に追いこまれるかということを、ブリダの精神病院の患者たちを通して誰よりもよく知っていたのはファノンであり、また、ファノンはそういった状況を変えるためにFLNに身を投じたはずであった。しかし、このメルーザの事件は、そのファノンの思いを踏みにじるような出来事であった。
事件の2日後、ファノンはFLNのスポークスマンとして、事件の犯人はフランス当局だとする嘘の声明を発表した。このとき、ファノンが事件の真相を知っていたかどうかは定かではない。しかし、「文化とポストコロニアル批評ⅡL」の授業によると、1959年に発表された『革命の社会学』の序文の「避けなければならなかったこと」(Fanon,1984,p.5)という部分がメルーザの虐殺事件を指しており、このときすでにファノンは真相を知っていたとする考え方もある。もしそれが正しいとするなら、ファノンは恐らく、メルーザがエスニックマイノリティーであるベルベル人の村であったということも知っていたはずである。この許されざる事態がどういう経緯で発生したのか、FLNのスポークスマンであるファノンには当然知る権利があり、また、知らねばならなかったであろう。そして、この事件をきっかけに、彼はベルベル人に対する迫害に気づき始めたと考えられる。さらに、この頃にはすでに「ベルベル主義者騒動」などのベルベル問題に関心を持っていたという可能性もある。
9. 国境のベルベル人難民
FLNのスポークスマンとしての活動と同時に、ファノンはアルジェリアとチュニジアの国境地帯で医療活動を行っていた。このころ、フランス軍の強制収容所から逃れるために約百万のアルジェリア人が、西のモロッコや東のチュニジアとの国境地帯に流入し、難民となっていた(海老坂,1981,p.199-200)。そして、ファノンがいたチュニジアとの国境地帯にはアラブ人難民だけではなく、ベルベル人難民もいたであろうと考えられる。ファノンがはじめてベルベル人と接触を持ったのは、おそらくこの国境地帯での医療行為を通してであろうと考えられる。
その根拠は、『地に呪われたる者』のなかの精神障害の症例として「S」という人物の症例があり、彼が「コンスタンチーヌ地方のある村に居住」(Fanon,1969,p.148)していた人物であったということである。コンスタンチーヌ地方は、ベルベル人の村、メルーザがあった場所である。したがって、おそらく「S」もメルーザ村の住民と同じベルベル人だったのであろう。
なぜならば、8世紀以来アラビア語の浸透によって追いやられた「ベルベル語は山岳地帯の孤立した地域で保存され」(Chaker,2000,p.187)ていたからである。また、コンスタンチーヌ地方は、アルジェなどの都市とは違い比較的内陸の孤立した場所に位置している(Roy,1961,p.ⅷ)。こうしたことから、コンスタンチーヌ地方はベルベル語を話す人々が、他の地域から孤立して暮らしていた場所であった可能性が高い。
『地に呪われたる者』の精神障害の症例には一部ブリダの病院時代のものもあるが、「S」が精神障害を負った原因となった事件は1958年のことであり、ファノンがブリダの病院を辞めた1956年よりも後のできごとである。したがって、「S」はファノンが国境地帯で診察した患者である。モロッコとの国境へ向かった難民も多かったであろうが、約百万という難民全体の数の多さを考えると、彼と同じようにコンスタンチーヌ地方からチュニジアとの国境地帯へ逃げ、難民となったベルベル人がいたとしてもなんの不思議もない。また、ベルベル人と同じように、方言アラビア語を話すアラブ人も国境地帯にいたであろう。
ファノンが既にメルーザ村の惨劇の真相を知っていたとするならば、彼がベルベル人難民に興味を抱かないはずはない。なぜなら、彼の怒りは常に差別や弾圧に向けられており、たとえアルジェリアの独立という目標のために今は目をつぶらなければならず、FLNのスポークスマンという立場からその思いを公にできなかったのだとしても、フランスで実際に差別を受けてきたファノンには彼らに対する同情や共感があったはずだからである。したがって、こういった人々への診察という行為を通して、ファノンがベルベル人の弾圧の実情を知っていったという可能性は大いにある。
10. 異邦人ファノン
また、ファノンがアルジェリア人でなかったことも、彼がベルベル人に対して同情・共感の念を抱いた理由の一つであろうと考えられる。ファノンは外国人であり、かつアラビア語を話すことができなかったからである。
ブリダにいた頃、精神科医としてアラブ人患者の治療にあたったファノンは、診断や治療のために、とりわけ彼が行おうとした社会療法のために、アラビア語が必要であった(海老坂,1981,p.156)。そのため、ファノンはアラビア語を学び始めた。
しかし、
「ジャンズィアーによればそれは失敗、ゲイスマーによれば、患者の言うことをほぼ理解しうるまでに進歩した。いずれにせよ、二、三年の勉強では、通訳を必要としないところまではいかなかった」(海老坂,1981,p.156)
ようである。
また、アルジェリアでは様々な急進的ナショナリストグループが、言語的・文化的な多様性を拒否する傾向を強化しており(Chaker,2000,p.190)、ファノンの所属していたFLNもその例外ではなかった。FLNのスポークスマンであったとはいえ、アルジェリア人ではなく、アラビア語も話せないファノンは、アルジェリアに来た当初、またはFLNの活動に参加して間もない頃はアラビア人から差別を受けていた可能性がある。
ファノンがアラビア人から差別を受けたことがあるとすれば、それはベルベル人が受けていた差別と同じ、アラビア語を話すことができない者たちに対しての差別である。たとえ、ファノンがアラビア語を少しは扱えたのだとしても、急進的なアラブ人たちからは低く扱われたであろう。こうしたことを考えると、ファノンがベルベル人に対して同情・共感の念を抱いていたとしてもなんの不思議もない。
11. 『革命の社会学』にみる「全的人間」の兆候
メルーザの虐殺、ベルベル人難民への医療行為などを通して、ファノンはベルベル問題について知るようになったのであろう。そして、そうした経験がファノンの思想に変化を与えたのである。
1952年に発表された『黒い皮膚・白い仮面』の第5章「黒人の生体験」について、海老坂は「この章の最後の数ページは、このサルトルの『黒いオルフェ』との対決の記録として読める」(海老坂,1981,p.240)と述べている。また、この章のなかでファノンは
「黒人のニグロ意識自体が一つの肯定性、絶対性であることを主張し、それが弁証法の一モメント、否定的契機に還元されることを拒否」(海老坂,1981,p.240)
している。
このように、1953年にアルジェリアに転勤するまでのファノンは「ネグリチュード」に固執していた。
しかし、1959年に発表された『革命の社会学』の序文には、アルジェリアに転勤する以前の、「ネグリチュード」に固執していた時期のファノンには見られなかった記述がある。
それは、
「拷問するヨーロッパ人民は堕落した人民であり、その歴史を裏切っている。拷問をする後進国人民は、[後進性という]自己の本性を肯定し、後進国人民としての仕事を行っていることになる」(Fanon,1984,p.6)
という記述に現れている。
この文章には、植民者であるヨーロッパ人への非難とともに、過ちを犯したものは、たとえ仲間であってもそれを弾劾するという意志が現れている。これは、「皮膚の色をしかと直視した上で、なおかつ白-黒を超えて」(海老坂,1981,p.25)、一人の人間を評価しようという、「全的人間」にきわめて近い考え方である。
また、「植民地主義の死とは、被植民者の死であると同時に植民者の死である」(Fanon,1984,p.14)という記述や、「われわれアルジェリア人が望んでいることは、植民者の背後から人間を引き出す[発見する]ことである」(Fanon,1984,p.14)という記述などにも、違いを越えて相手を理解し、同じ「人間」であろうとする「全的人間」の思想が現れている。
こうして、『革命の社会学』のなかに現れ始めた「全的人間」の思想は、後に『地に呪われたる者』において顕在化することになるのである。
12. 「全的人間」への移行
もしも、ファノンが黒人性の強調である「ネグリチュード」が正しいと考えていたとしたら、アルジェリアでも「アラブ・ナショナリズム」を打ち立てるだけでよったはずである。それにも関わらず、ファノンの思想は「ネグリチュード」から、最終的に『地に呪われたる者』に現れるような、「全的人間」へと変化した。そのきっかけを与えたのはサルトルの「黒いオルフェ」であった。
しかし、その最大の契機となったのは、メルーザの虐殺事件、国境地帯でのベルベル人難民との接触などを通して、フランスとの戦いの裏側で、アルジェリア内部にも差別や抑圧があることをファノンが知ったためであろう。もしかすると、ファノンがベルベル主義者騒動を知っていたということや、彼自身アルジェリアに来た当初アラビア語を話せないことに対する差別を受けていたということも考えられる。
いずれにせよ、ベルベル問題を知ることによって、ファノンは「ネグリチュード」と同様の「アラブ・ナショナリズム」を掲げてアルジェリア解放闘争に勝利したとしても、その後はアラブ系住民によるベルベル人への弾圧と抑圧というフランスによる支配と変わらない状況が再び繰り返されることになるだろうということに気づいたのである。
そこではじめて、ファノンはサルトルの言う「ネグリチュードは己を破壊する性質のものであり、経過であって到達点ではなく、手段であって最終目的でない」(富山,1996,p.99)という言葉を受け入れることができたのであろう。
ところで、ジャン・ジュネの原作をフランス人演出家フレデリック・フィスバックが人形芝居にした『屏風』という作品がある。ジャン・ジュネ原作の『屏風』は、「1961年にベルリンで初演され、66年にパリのオデオン座で上演された際には、アルジェリア独立戦争(54~62年)に対する風刺・批判が含まれていたために大スキャンダルとなった芝居」(小崎,2005.1.21取得)である。
〔この人形劇は、〕宗主国フランスにいるフランス人、そこから派遣された軍人、北アフリカに移住した入植者たち、入植者たちが搾取するアラブ人、アラブ人が馬鹿にするベルベル人……といった差別の連鎖(小崎,2005.)〔を描き出した作品である。〕
ファノンが見出したアルジェリア内部の矛盾とはまさにこの「差別の連鎖」であったのだろう。これを乗り越えるために、ファノンは「全的人間」へと進んでいくことを決意したのである。
13. 「全的人間」のその後
ファノンが「ネグリチュード」の誤りに気づき、「全的人間」へとその思想を変化させ、同時に新しいアルジェリアもそのように導いていこうとしていた努力は今のところ実を結んでいない。
1961年にファノンが亡くなり、翌年の1962年にアルジェリアが独立した後、フランスという敵がいなくなった代わりに、アラブ対ベルベルの緊張状態は1963年のベルベル語使用地域であるカリビー地方に支持を持つFFS(社会主義者戦線)による武装蜂起や、1974年の「爆弾テロ首謀者」事件、1974年の「キャップ・シグリ事件」などへと発展していき、(Chaker,2000,p.194)現在もそれは続いている。
<おわりに>
ここまで述べてきたように、1953年にアルジェリアに転勤するまでのファノンは「ネグリチュード」に固執しており、「全的人間」への変化の兆候が現れるのは、1959年に発表された『革命の社会学』の文章のなかである。それゆえ、この1953年から1959年の間にファノンの思想を「ネグリチュード」から「全的人間」へと変化させた原因があるはずである。1953年から1959年の間にファノンが経験したことは、メルーザの虐殺事件や、チュニジアとの国境でのベルベル人難民への医療行為などのベルベル人に関することであった。
したがって、ファノンの思想を「ネグリチュード」から「全的人間」へと変化させた原因は、彼がアルジェリアにおけるベルベル問題を知り、「ネグリチュード」や「アラブ・ナショナリズム」のような自己第一主義的な考え方では、たとえ植民地主義は打倒できても、結局、差別や抑圧がなくなることはなく、また新たな火種となるだけだということに気づいたからである可能性が高い。
参考文献
Kevin Bales.(大和田英子 訳).(2002).グローバル経済と現代奴隷制.凱風社.pp.116-133.
三浦信孝.糟谷啓介 編.(2000).言語帝国主義とは何か.
シャリム・シャキール〔Salem Chaker〕.(鶴巻泉子 訳).アラビア語化の中のベルベル語:マグレブ、とくにアルジェリアの場合.藤原書店.p. 187, 188-189, 190, 191, 194, 198.
Frantz Fanon.(宮ヶ谷徳三 他訳).(1984).革命の社会学.(フランツ・ファノン著作集2).みすず書房.p. 5, 6, 14.
Frantz Fanon.(鈴木道彦.浦野衣子 訳).(1969).地に呪われたる者.(フランツ・ファノン著作集3).みすず書房.p.148.
ジュール・ロワ〔Jules Roy〕.(鈴木道彦 訳).(1961).
アルジェリア戦争:私は証言する.(岩波新書青版421).岩波文庫.p.ⅷ.
海老坂武.(1981).フランツ・ファノン,(人類の知的遺産78).みすず書房.p. 24, 25, 115,121, 122, 123, 124, 143, 156, 186, 187, 191, 199-200, 240.
冨山一郎.(1996).対抗と遡行:フランツ・ファノンの叙述をめぐって.岩波書店.思想,866:99.
CIA.The World Factbook:People's Democratic Republic of Algeria .(2005.1.13更新).(http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ag.html).2005.1.21取得.
外務省.各国・地域情勢:アルジェリア民主人民共和国.(2005年1月 現在).(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/algeria/data.html).2005.1.21取得.
Japan Knowledge.私市正年.日本大百科全書:ベルベル(人).(http://na.jkn21.com/cgi-bin/auth/snshowbody?nm_userID=&nm_itemNo=0021094800&nm_query=%A5%D9%A5%EB%A5%D9%A5%EB&GJ=IMG&nm_operator=and&nm_notStrongFlag=0&nm_trigger=oneLookSearch&USER_ID=&STRKEY=&START_PAGE=&TERM=&CHARGE_FLG=&OPE_FLG=&RELATION_FLG=&SITE_DATA1=&SITE_DATA2=&SITE_DATA3=&SITE_DATA4=&SITE_DATA5=&SITE_DATA6=&SITE_DATA7=&SITE_DATA8=&SITE_DATA9=&SITECHK_FLG=&SEARCH_FLG=&FONTGIF_FLG=).2005.1.21取得.
小崎哲哉.『屏風』について.(http://www.realtokyo.co.jp/japanese/column/ozaki41.htm).2005.1.21取得.
- (Frantz Fanon(フランツ・ファノン)(Image by Pacha J. Willka at Wikimedia Commons))[Back ↩]






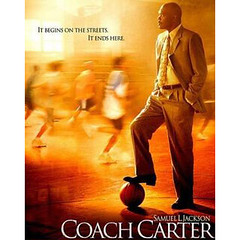







とても役に立ちました。ありがとうございます。
まみさん
こんにちは、倉田幸暢です。
コメントありがとうございます!
なにかのご参考になればうれしいです。
m(_ _)m